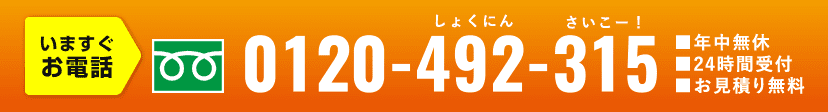日本は台風や集中豪雨による浸水被害が毎年のように発生しています。
9月12日に発生した記録的な大雨で、三重県四日市市にある地下駐車場が水没したニュースに衝撃を受けた方も多くいらっしゃると思います。
そしてこのニュースを見て、ご自分の近くで記録的な大雨が降った場合、どうやって水没を防げばよいか考えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
大切なご自宅を守るためには、災害が起きる前に適切な準備を行っておくことが何より重要です。
水害は一度発生すると建物や水まわり設備に深刻なダメージを与え、多額の修繕費用も発生してしまうのです。
今回は、家を浸水させないために事前にできる備えについてご紹介します。
目次
水害が家にもたらす被害の大きさ

水害が発生すると床下や床上に水が流れ込み、建材や内装を腐食させます。
床材や壁紙は水に弱く、一度浸水すると乾燥しても強度が低下してしまうのです。
また、土砂やごみなどが混ざった汚水を吸収しているため、乾いた後も悪臭が残る恐れがあるでしょう。
さらに湿気がこもることでカビが発生し、健康被害にもつながります。
水害の被害はこれだけに留まらず、浸水は水まわり設備に大きな負担を与えます。
トイレや排水口からの逆流や給水管の破損、下水の逆流などが代表的なトラブルです。
こうした被害を避けるためには、あらかじめご自宅周辺の水害リスクを把握し、対策を講じておくことが大切です。
関連記事:なぜ夏から秋は台風が多いのか?台風後に注意すべき水まわりトラブルも【水道職人:公式】
浸水リスクを把握することが第一歩

まず大切なのは、ご自宅周辺がどの程度浸水のリスクを抱えているかを知ることです。
自治体が公表しているハザードマップを確認することで、河川の氾濫や内水氾濫の危険度を把握できます。
また、過去に浸水があった地域や、排水設備が古い地域では特に注意が必要です。
リスクを正しく理解しておくことで、具体的な対策に優先順位をつけられます。
備えは一律ではなく、ご自宅の立地や環境に合わせた準備が重要です。
排水設備を整えて浸水を防ぐ

浸水被害を防ぐには、排水が正常に行われる状態に整えておくことが欠かせません。
雨水を効率よく流すために、側溝(そくこう)や排水口に溜まった落ち葉・泥などのごみを取り除きましょう。
ご自宅の敷地内にある排水マスやグレーチングも定期的に掃除することで、水が滞留することを防げます。
また、庭や駐車場にある排水口がつまっていると、雨水が溢れて家屋に流れ込む可能性が高まります。
台風や大雨の予報が出た際は、必ず事前に点検しておくことがおすすめです。
これらの対策は大雨の予報が出ているときだけではなく、日常的に行うべき大切なメンテナンスでもあります。
近年、突然大雨が発生するケースも度々あるため、日常的にメンテナンスを行っておくことで、突然の大雨でも浸水を予防できるのです。
水まわりは日常生活に直結する大切な部分です。
災害時の備えとしても特に重点を置いた方がよいでしょう。
水まわりの排水機能を維持する屋外対策

水まわりの排水機能を維持するために、屋外対策は必要不可欠です。
以下のポイントを押さえて対策を講じてください。
【屋外で行う排水対策】
- 雨どいや樋(とい)の清掃を徹底する
雨どいがつまると雨水が溢れ、外壁や基礎を伝って水まわりに流入。
特に台風シーズン前には落ち葉や泥を除去する習慣をつけましょう。
- 外部排水口やグレーチングの点検
敷地内外にある排水口や排水マス、グレーチングのつまりが浸水の原因になることがあります。
定期的に泥や落ち葉を取り除き、排水経路を確保しておきましょう。
- 土のうや水のうの活用
浸水が予想される場合、水まわり設備の配管出口や給湯器周辺に設置しておくことで、浸水被害を抑えられる可能性があります。
簡易式の吸水土のうなら保管も容易で、いざという時にすぐに使用できるでしょう。
- 外構と排水勾配の見直し
駐車場や庭の排水が悪いと、水が建物へ流れ込みやすいという問題が発生します。
過去に浸水被害を経験している場合、排水勾配や排水管の高さ調整を水道修理業者に相談することも対策として有効です。
関連記事:台風に備える!ベランダ排水溝のつまりチェックとメンテナンス【水道職人:公式】
浸水を防ぐための屋内の水まわり対策

水害による浸水対策は、屋外だけではなく屋内でもしっかりと対策を講じることが求められます。
以下のポイントを押さえて対策してください。
【屋外で行う浸水対策】
- 排水口の逆流防止
浸水時には下水が逆流し、トイレや浴室の排水口から汚水が噴き出すことがあります。
専用の逆流防止弁や止水キャップを設置しておくことで、被害を防げるでしょう。
- 排水ポンプの準備
洗面所や浴室の床に水が溜まるリスクがある場合、ご家庭用の排水ポンプが有効です。
ホースを組み合わせて屋外に排水できるようにしておきましょう。
- 防水シートやパッキンで隙間を防ぐ
洗面台下や浴室の縁、洗濯機パンまわりは隙間から水が浸入しやすい場所です。
防水シートを敷いたり、劣化したゴムパッキンを交換したりしておくことで、隙間が発生しにくくなります。
- 水まわり設備の位置を高めに設置
洗濯機は防水パンを底上げし、給湯器はできるだけ高い位置に設置することで、浸水被害を予防できます。
数センチの差でも浸水の被害は軽減できるのです。
- 配管まわりの隙間を塞ぐ
壁や床を貫通する給水管や排水管の周囲は、浸水の経路になってしまう可能性があります。
防水シールやモルタルで隙間を塞ぎ、外部からの浸水を予防しましょう。
トイレや排水口の逆流を防ぐ方法

水害時には下水管が圧迫され、トイレや排水口から水が逆流することがあります。
この逆流は悪臭や衛生問題を引き起こし、復旧作業には日数を要するでしょう。
また、被害状況次第ではトイレ空間だけに留まらず、トイレに面した廊下や部屋も修繕が必要となるケースがあり、膨大な日数だけではなく多額の費用負担も発生する恐れがあります。
対策としては止水栓を閉めておいたり、排水口に排水逆流防止器を設置しておいたりするといった方法があります。
特にマンションなどの集合住宅では、下層階ほど逆流被害のリスクが高いため注意が必要です。
上層階にお住まいの方は、ご自宅ではなく下層階の方の部屋で逆流が発生するケースがあるため、集合住宅から排水の使用禁止令が出たときは従うようにしてください。
水まわりの逆流対策は専門的な知識が必要な場合もあるため、不安な方は水道修理業者に相談しておくと安心です。
みんなの町の水道職人でも、排水設備の点検や逆流防止の施工に対応しております。
排水に不安があるときは、お気軽にご相談くださいませ!
窓やドアからの浸水を防ぐ工夫

浸水は排水口からだけではなく、窓やドアの隙間からも発生します。
特に地面に近い場所に設置された窓(地窓・掃き出し窓など)や、地下室の窓は水の侵入口になりやすいので注意が必要です。
窓やドアからの浸水対策には、土のうや止水板を準備しておくとよいでしょう。
土のうは水を含むと重くなり、水の侵入を防ぐ障壁として機能します。
最近では、水を吸収して膨らむ簡易タイプの土のうも市販されており、保管スペースも取らず手軽に使用できます。
また、窓やドアのパッキンが劣化していると、少量の雨でも室内に水が入り込みます。
事前に点検して、必要があれば交換しておきましょう。
電気設備の浸水対策

水害では電気設備の被害も深刻です。
コンセントや分電盤が浸水するとショートや火災につながる恐れがあり、大変危険です。
そのため、床に近い位置にあるコンセントには防水カバーを取りつけたり、延長コードなどを床から離す工夫が必要です。
また、浸水が予想される場合は電化製品を高い位置に移動させましょう。
冷蔵庫や洗濯機などの大型家電は移動が難しいですが、延長台を使用して数センチでも高くしておくと浸水被害を軽減できる可能性があります。
浸水時に備えた備品の準備

万が一に備えて、止水板や簡易土のう、防水テープなどの備品を事前に準備しておくと、大雨の予報が出たときに慌てずに浸水対策を行えます。
これらはすぐに設置できるため、浸水の被害を軽減できる優秀な道具です。
また、懐中電灯や非常用トイレ、飲料水、食料品の備蓄も忘れてはいけません。
水害はライフラインを断絶させる恐れがあるため、数日分の備蓄を確保しておくと安心です。
水害対策は日常の点検から始めよう

浸水を完全に防ぐことは難しいですが、事前の対策によって被害を大幅に軽減できます。
日常的に排水口の掃除や水まわり設備の点検を行い、異常を早期に発見する習慣をつけましょう。
また、大雨や台風が接近する際には、ご自宅の水まわりや排水設備の点検を優先的に行うことをおすすめします。
小さな準備の積み重ねが、大切な家を守る大きな力になります。
私たちみんなの町の水道職人は、水まわりの修理やメンテナンスだけではなく、災害時の不安ポイントについてもご相談を承っています。
浸水対策は専門的な知識と経験が必要になる部分も多いため、排水不良などの不安を感じる場合はぜひご相談ください!
地域に根ざした対応で、皆さまの安心できる暮らしを支えてまいります。