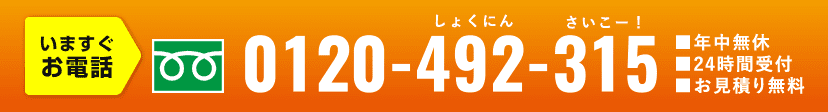花粉症の季節がやってきましたね。
2025年はスギ花粉のピークが3月頃、ヒノキ花粉のピークが3月下旬~4月頃だと言われています。
約2カ月間、花粉症の方にとってはしんどい時期が続きますね。
花粉症の診断を受けている方や、花粉症の疑いがあると感じている方は、花粉症対策として、掃除に力を入れているのではないでしょうか。
リビングなどの居室はしっかりと掃除していると思います。
この際、トイレや洗面所といった衣類を着脱したり、帰宅後に直行したりする場所の掃除も行っていますか?
実は、トイレや洗面所は意外に花粉がたまりやすい場所だと言われているのです。
今回は、花粉症対策のために掃除しておきたい場所や、通気口の花粉症対策についてご紹介します。
目次
これが大事!花粉は家の中に持ち込まない
花粉症の対策で最も大事なことは、花粉を家の中に持ち込まないということです。
家の中に落ちた花粉は丁寧に掃除しないと残り続けてしまいます。
そのため、帰宅後は玄関でアウターなどを脱ぎ、衣類用の粘着シートで花粉を取り除き、毛並みの整えと最後の仕上げのためにブラシをかけましょう。
また、カバンなどの外に持ち出していた服飾品にも花粉は付着しています。
衣類用の粘着シートだと粘着物が残ってしまうかもしれないと不安を抱く材質の場合、ウェットシートや濡れタオルなどで優しく花粉を拭き取りましょう。
ただし、花粉を取り除くためにパタパタと叩くことはNGです。
花粉を持ち込まないために玄関前でアウターを脱いで、パタパタと花粉を叩く方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、叩くと花粉が舞い、目や鼻に花粉が入ってしまいますし、衣服やカバンなどにも付着します。
花粉の影響を少しでも抑えるために、優しく、花粉が舞わないように注意を払うことが大切です。
そして、アウターを玄関の外で脱ぐと、アウターの下に着用している衣服に花粉が付着します。
そのため、アウターは玄関の外で対処したからとそのまま室内に入ってしまうと、衣服に付着した花粉が室内に侵入します。
アウターを脱いでいる時間は短時間だったので大丈夫と、安心しない方が良いでしょう。
花粉対策は朝の掃除が効果的!
誰も稼働していない時間帯は、空中に舞いあがっていた花粉やホコリなどが床に落ちると言われています。
起床後の誰も動き出していない時間や、数時間は誰もいなかった状態の帰宅後は、花粉を除去する格好のチャンスです。
起床後に時間が取れないときは、帰宅後に家中を掃除してみてください。
床掃除
床掃除に使用するアイテムは、フローリングワイパーなどの、花粉やホコリが舞い上がりにくい掃除道具がおすすめです。
人が動き始めると空気の流れができてしまい、落ちていた花粉やホコリは空中に舞い戻ります。
少しでも空気の流れが少ない方法で掃除した方が良いのです。
フローリングワイパーを使用するときは、ドライタイプではなくウェットタイプの方が、より花粉を取り除きやすいでしょう。
フローリングで使用できる粘着シートをお持ちの場合、粘着シートも有効です。
ただし、フローリングでも使用できると謳っている製品以外の粘着シートは、フローリングに貼り付いて塗装を剥がす可能性があるため、使用は控えましょう。
壁やカーテン・ソファ・カーペットなど
壁やカーテンなどの壁面、ソファやカーペットなどの人間がくつろいだり歩いたりする場所も、花粉が付着します。
壁はハンディワイパーを使って掃除しましょう。
この際、ハンディワイパーにアルカリ電解水などを吹き付けて、濡らしてから拭くことで花粉が舞い散りにくくなり、壁の汚れも拭き取れます。
カーテンやソファ、カーペットなどは、粘着シートを使用して掃除すると良いでしょう。
ただし、カバーの種類やカーペットの種類によっては、粘着シートを使用すると毛が抜けてしまうというケースがあります。
このような場合には、掃除機で吸い取ることも可能です。
花粉が舞い散らないように、ゆっくりと丁寧に掃除機をかけてください。
トイレや洗面所・脱衣所
トイレや洗面所・脱衣所は、帰宅後すぐに入ることや、衣類を着脱する場所であることから、意外に花粉がたまりやすいのです。
なぜ花粉がたまる?
外で付着する花粉は、外を歩いている時だけではなく、飲食店などの屋内でも付着します。
多くの方は、屋内ではアウターを脱いでいるのではないでしょうか?
アウターを脱いでいる時間は、アウター以外にも花粉が付着してしまっているのです。
トイレは排泄のためにボトムスを着脱し、脱衣所ではお風呂に入るために衣類を脱ぎ、洗面所は手洗いのために帰宅後すぐに入ることが多い空間です。
これらの際に、花粉が落ち、ホコリと同様に隙間などに入り込み、花粉症の症状を引き起こします。
また、トイレマットやバスマット、便座カバーなどの布類にも、花粉が付着してしまいます。
バスマットを撤去することは難しいですが、トイレマットや便座カバーは、花粉症の時期は使用しないとことで、花粉が入り込みやすい場所を減らせます。
掃除はどうすれば良い?
トイレや洗面台、洗濯機などに花粉が付着するため、掃除のときはウェットシートで表面を優しく拭き取りましょう。
トイレの便座は、ドライシートで拭くと傷が付いてしまうケースがあります。
花粉を除去するだけではなく、便座を傷から守るためにも、しっかりと濡れているシートを使用しましょう。
床はフローリングワイパーを使用してください。
トイレを掃除するときは、クエン酸スプレーなどをドライシートに吹き付けてから磨くと、アンモニアの汚れやニオイも除去できます。
壁はハンディワイパーを使用してください。
床と同様に、クエン酸スプレーなどを吹き付けることで、壁に付着したアンモニアの汚れが対策できます。
トイレマットやバスマット、便座カバーは粘着シートで花粉を取り除いてください。
マットの毛足が長い物を使用されているご家庭では、奥に入り込んでしまって粘着シートでは取り除けないことがあります。
掃除しているのに花粉の症状が出る場合、粘着シートで取り除くのではなく、毎日洗濯した方が良いでしょう。
通気口(給気口/吸気口)は閉めない
ご自宅に通気口がある方は、花粉の出入り口となるため、閉めたいと考えるかもしれません。
しかし、安易に閉めることは控えた方が良いでしょう。
通気口はとても大事な役割を持っているのです。
通気口を閉めるリスク
2003年以降に建築された住宅では、24時間換気システムが設置されています。
そして、同時に通気口も取り付けられています。
現代の住宅は気密性が高く、防音性にも優れるでしょう。
一方で、住宅の中は空気がこもりやすく、ダニやカビの発生を促し、シックハウス症候群が発症するリスクが高まります。
このシックハウス症候群が発症するリスクを軽減するために、2003年に建築法が改正され、24時間換気システムをすべての建築物で設置することが義務付けられました。
そして、通気口には新鮮な空気を取り入れる役割があります。
多くの住宅に設置されている24時間換気システムは、通気口から取り込んだ新鮮な空気を、トイレや浴室に設置された排気ファンから排出します。
そのため、通気口を塞ぐと空気を取り入れられなくなり、排出のみの働きが行われるでしょう。
その結果、頭痛や吐き気といった体調不良があらわれる危険があるのです。
花粉の対策や、寒いなどの理由でどうしても塞ぎたいときは、長時間塞ぎ続けるのではなく、1時間に1回空気を取り入れる時間を作るために、通気口を開けるなどの対策を施してください。
後付けフィルターで花粉キャッチ
通気口専用の、花粉をキャッチできるフィルターがあることをご存じですか?
アレルブロックや換気口フィルター、空気清浄フィルターなど、さまざまな名前で販売されているこのフィルターは、ホームセンターや通信販売で購入できます。
使用方法は簡単で、通気口に貼り付けるだけで、花粉やPM2.5だけではなく、防虫効果もあるでしょう。
中にはハサミでカットが必要な物もありますが、大きい通気口でも使いやすいというメリットがあるでしょう。
交換目安は製品によって異なりますが、貼り付ける前と絵柄の色が変わったら交換の合図といったように、分かりやすい表示になっています。
また、仮にきれいな状態のままでも、3カ月を目安に必ず交換が必要などの注意書きも記載があるでしょう。
通気口を閉めて行う花粉対策は、体調を崩す危険がありますし、体調を崩さないようにするために24時間換気を止めてしまうと、シックハウス症候群のリスクが発生します。
健康被害への懸念を軽減するためにも、通気口を閉めるのではなく、開けたままで行える花粉対策を講じた方が良いのです。
▼花粉の時期にやっておきべき掃除について詳しく知りたい方はこちら
新生活のトラブルを未然に防ぐ!水回りのサクッとチェックリスト【水道職人:プロ】
花粉症は病院も頼りましょう!
花粉症に効果がある市販薬や目薬が薬局で手に入るため、通院はしていないという方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、症状が年々ひどくなっているときや、市販薬で効果を感じられないとき、市販薬では眠くなってしまうときなどは、医療機関を受診することもご検討ください。
医療機関で行っている花粉症の治療には、薬物療法やアレルゲン免疫療法、手術療法があります。
医療機関では、受診者の症状や生活環境などにより適した治療法の提案があるため、花粉症に苦しまない生活が送れるようになる可能性があります。
まだまだ花粉症シーズンは始まったばかりです。
しんどい期間が続きますが、無理をせずに乗り切りましょう。