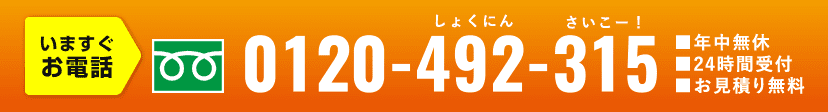浴室や洗面所、キッチンなどの水まわりは湿気がこもりやすく、カビが発生しやすい環境です。
うっかり見落としてしまったカビは、いつの間にか広がり、お掃除ではなかなか取れない頑固な存在になってしまいます。
今回は、水まわりにできてしまったカビの効果的な対処法と、再発させないための再発防止策をご紹介します。
できてしまったカビの見つけ方
カビは目に見える黒ずみとして現れることが多く、とくに浴室のタイル目地やシリコン部分、洗面ボウルの隅、キッチンシンクの裏側などに現れます。
しかし、初期段階のカビは薄いグレーやピンク色のヌメリとして現れることもあり、見逃しがちです。
また、カビ特有のカビ臭さを感じた場合も、目に見えない場所で繁殖している可能性があります。
定期的に水まわり全体をチェックし、少しでも違和感があればすぐに対処することが大切です。
▼定期的な水まわり掃除に関して詳しく知りたい方はこちら
水まわりの掃除・手入れができる日用品は?便利な道具を紹介!【水道職人:公式】
できてしまったカビの対処法
すでに発生してしまったカビには、適切な方法でしっかりと対処することが重要です。
カビは根を張る性質があり、表面を拭いただけでは見た目はきれいになっても、根が残って再び繁殖することがあります。
対処法1. 塩素系漂白剤を使う方法
黒カビに最も効果的とされているのが、塩素系漂白剤を使った方法です。
市販のカビ取り剤や、台所用漂白剤などを使って、強力にカビを分解殺菌します。
塩素系漂白剤の使い方
- 換気をしっかり行い、ゴム手袋とマスクを着用
- 対象部分のホコリや汚れを簡単に水で落とす
- スプレータイプの塩素系漂白剤を、カビのある部分に直接噴霧
- しつこいカビには、キッチンペーパーを貼ってからスプレーし、ラップで覆う湿布法が効果的
- 10〜30分程度放置したら、水でしっかり洗い流す
塩素系漂白剤の注意点
金属やゴムの劣化、色落ちを引き起こす可能性があるため、目立たない部分で試してから使うと安心です。
また、塩素のニオイが強いため、換気扇を回したり窓を開けたりして、作業してください。
なお、酸性タイプの洗剤やクエン酸と混ぜることは厳禁です。
万が一混ざってしまうと、有毒ガスが発生する恐れがあり大変危険です。
排水口の中で混ざる可能性を予防するために、酸性タイプの洗剤やクエン酸を使って掃除したい場合には、別の日に行った方が良いでしょう。
対処法2. 酸素系漂白剤で優しく落とす
酸素系漂白剤は、過炭酸ナトリウムを主成分とし、塩素系漂白剤よりも刺激が少なく、環境にも優しい洗浄成分です。
カビを落とす力はやや弱いですが、殺菌除菌効果があり、とくに衣類や木材、プラスチック製品など、色落ちや腐食が気になる素材に適しています。
酸素系漂白剤の使い方
- 40〜50℃程度のぬるま湯に、酸素系漂白剤を溶かす(1リットルあたり小さじ2〜3程度)
- 布に浸して絞ったり、直接カビ部分に塗布したりする
- 30分程度置いてから、スポンジやブラシで優しくこすり、洗い流す
酸素系漂白剤のおすすめの使い方
歯ブラシや排水口カバーなどの小物類にも、酸素系漂白剤はおすすめです。
バケツや洗面ボウルで漂白液を作り、小物類を浸け置きすると、カビ汚れや予防に効果的です。
対処法3. 重曹とクエン酸を使った自然派掃除
小さなお子様やペットがいるご家庭では、できるだけ安全性の高い方法を選びたいという方も多いのではないでしょうか。
そのような場合には、重曹とクエン酸を使った、ナチュラルクリーニングがおすすめです。
重曹とクエン酸がおすすめな理由
重曹は弱アルカリ性で皮脂や油汚れに強く、クエン酸は酸性で水垢や石けんカスの分解に効果的です。
この2つを組み合わせることで、発泡作用により汚れを浮かせ、軽度のカビであれば除去できます。
重曹とクエン酸の使い方
- カビができてしまった部分に、重曹をまんべんなくふりかける
- 重曹の上からクエン酸水(クエン酸小さじ1に対して水100ml)をスプレーする
- しゅわしゅわと泡が発生するので、そのまま10分程度放置
- スポンジや古くなった歯ブラシで優しくこすって、水で流す
重度の黒カビにはやや力不足ですが、日常の軽いカビ予防や、頻繁に使う場所のこまめな掃除には最適です。
対処法4. スチームクリーナーで根こそぎ除去
高温スチームを利用して、カビの根まで殺菌洗浄する方法もあります。
スチームクリーナーは熱だけで洗浄できるため、薬剤を使いたくない方にもおすすめです。
とくに、タイルの目地や窓枠のゴムパッキン、洗面所のプラスチック部などに有効です。
使用時は火傷に注意し、対象素材が熱に耐えられるかを確認してから行ってください。
スチーム後に布で水分をしっかり拭き取り、乾燥させるこも忘れないようにしましょう。
対処法5. プロの業者に依頼する選択肢も
広範囲にわたるカビや、何度掃除しても再発するカビ、天井裏や壁内部など手の届かない場所のカビには、プロのカビ除去業者に依頼するのも一つの方法です。
専門の機材や薬剤を使用し、再発防止まで含めた施工をしてくれるため、根本的な解決が可能になります。
料金はかかりますが、健康被害や建材へのダメージを考えれば、費用対効果は高いケースも少なくはありません。
場所別のカビ予防

カビは可能な限り発生させないことがベストです。
カビの予防方法は場所によってそれぞれ異なるため、適した方法で予防しましょう。
浴室の場合
浴室は最もカビが発生しやすい場所です。
使用後には冷水をかけて湿度と温度を下げ、スクイージーやタオルで水気を拭き取りましょう。
浴室乾燥機や換気扇を利用して、湿気を外に逃がすことも重要です。
とくに、シャンプーやボディソープのボトル裏はカビがつきやすいので、定期的に持ち上げて掃除しましょう。
洗面所の場合
歯ブラシスタンドや石けん皿の下、蛇口の根元などにカビが潜んでいます。
濡れたままの歯ブラシやコップを放置せず、使い終わったらしっかり乾かすようにしましょう。
また、排水口は週1回を目安に、パイプ用洗浄剤や重曹+クエン酸で掃除するのがおすすめです。
キッチンの場合
シンク周辺は常に濡れているため、カビの温床になりがちです。
とくに、三角コーナーや排水口のカバー裏、シリコンパッキン部分は念入りにチェックしましょう。
食器を洗った後は水気を拭き取り、シンクも乾燥させておくと清潔に保てます。
まな板や布巾はしっかりと乾かし、こまめに漂白して清潔を保ちましょう。
カビの再発を防ぐ予防策
カビは1度除去しても、油断すれば再発してしまう厄介な存在です。
カビを除去した後は、再発しないように予防策を講じましょう。
予防策1. 毎日のこまめな換気
湿気をためないために、浴室を使ったあとは、必ず換気を行いましょう。
換気扇は入浴後最低1時間は回すことがおすすめです。
窓がある場合は定期的に開けて、空気を循環させることも効果的です。
予防策2. 水気を残さない習慣づけ
水気が残っていると、カビはすぐに繁殖します。
水まわりを使ったあとは、壁や床の水滴を拭き取る、タオルやマット類はこまめに洗濯するなど、水分を残さないよう意識しましょう。
予防策3. 防カビグッズの活用
市販の防カビ燻煙(くんえん)剤やスプレー、防カビ剤付きのパッキンカバーなども、予防に効果的です。
定期的に使うことで、カビの根が入り込むのを防ぐことができます。
予防策4. こまめな掃除と点検
週に1〜2回は水まわりの汚れをチェックして、気になる部分を掃除する習慣をつけましょう。
小さな黒ずみも放置せず、早めに対処することで広がることを防げます。
また、ピンクカビ(ロドトルラ)は黒カビのエサになるため、見つけ次第掃除することで、カビの栄養源を断つことができるでしょう。
関連記事:梅雨こそ要注意!カビを発生させないための方法とは【水道職人:公式】
できてしまったカビは適切な方法で根絶を!
水まわりのカビは、発生してしまうと掃除が大変ですが、正しい方法で対処すれば除去することが可能です。
塩素系漂白剤や酸素系漂白剤、ナチュラルクリーナーをうまく使い分け、場所や素材に合った方法で丁寧に掃除しましょう。
また、日常的な予防習慣を取り入れることで、カビの再発や発生を防ぐことができます。
快適で清潔な水まわりを保つために、カビ対策を日々の生活に取り入れていきましょう。